
カタカムナ第58首は、いきなり「全体まとめ:サイドA」から
はじめちゃいます。
◆カタカムナ第58首を詠む
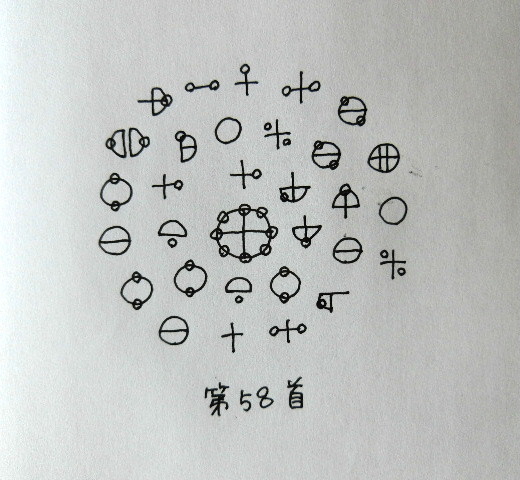
声に出して音を響かせイメージしましょう☆
【カタカムナ第58首】
オホトタマ タマル アハチホノサワケ
このウタ…なんとなく現代日本語からも意味を読めちゃいませんか?
そして、その示しは日本神話のままなのです。
①カムナ マニマニ~神御名
⇓
”神名のままに”
(神の御名 そのままに)
と、私の中では意味が見えてきたのです。
んで、この先を読み進めても意味がちゃんと通じてる=通るんだよね。
そこに示されていたことは
私が追っている「日本語の音のつくりの謎」や「日本の神々の不思議な名の謎」に
1つの答えを示してくれているかのような内容だったんです。
②カミワケノウタ
「神わけのウタ」とは?
私はさっそく、古語辞典で「わけ」を引いてみたのです。
⇓
古語辞典によると「わけ」とは、
”故(わけ)=素性・由緒・由来”とあったのです。
つまり、日本の神々の「御名」とは
”そのままに→ その神の素性を示している”わけです。
そかも、それは 「ウタ」になっていると…
「ウタになってる」…カタカムナの80首の歌々が
神の名とその神の素性を示しているということか?
それとも日本の神々の御名とは本来唄うように詠む・呼ぶべき
音の響きとリズムを持っているという事だろうか?
③オホトタマ タマル
ここは難解で古語からのイメージもすんなりは湧いてこなかった…
のですが「オホトタマ」を検索してみると
検索候補(類似語?)に「音霊・オトタマ」と出てきたのです!!
”神の名の音の響き”に、やはり特別な意味・意図があるわけかぁ。
その音の響きが、アマ界~カム界に響く壮大な歌の調べに作用している、とか。
更に「オホトタマ」を私は最初に「オオトタマ」と現代日本語感覚で読み
その後、こう変換したのです。
⇓
”オオミタマ=大御霊”
御霊=神霊、祖霊、霊威(霊魂の敬称でもある)
では、「大・御霊」とは何を示すのか?
ここで「オホト」の「ト」が活きてくるのです。
御霊が重合し大きく纏まったもの。
八百万の神々の「神霊の総体」といったイメージ。
それが「タマル」=珠として存在する、溜まる(=集まり、積もる)
~アハ地があるって云うんです!!
⇓
④アハチ ホノサワケ
私は最初「アハチ」と「ホノサワケ」を別々に調べてました。
古語辞典を「アハ」で引いてみると
⇓
「アハ」=多く、深く
ということはオホトタマ(音霊~大御霊)がタマル(溜まる~珠として存在する)
「アハの地」…それが「ホノサワケ」だと。
「ホノサワケ」ってどこや?
と思い、さっそく調べてみると、
”アハチホノサワケ=淡道穂之狭別”
が出てきて、なんと!
イザナギ&イザナミが国生みで生んだ大八島の最初の島のことだったのです。
「淡道穂之狭別島」とは「淡路島」のことだといわれています。
淡路島は国生みの第一島であり、
島国日本の島々の中でも「特別な存在」らしく
国生みの基盤「胞(え)」なのだそうです。
更に「別(わけ)」が持つ意味に注目!
人名に使われる「別」が当てられ擬人化されてり
島でありながら「神」でもあるのです。
こうして58首を詠んでみると
「淡路島」という場所がとても神聖で特別な地な気がして
私が思ってた以上に「何かある」ようなのです。
「国生み=クニ生み」の基盤にして「胞」なので
物質・現象的に何かあるはず…
というサイドAの読みを踏まえて
カタカムナの音の響きからの解読をスタート!
(つづく)

