
カタカムナ文献(歌)の解読をしつつ、
どうしても文字の形状・構造・法則性が気になり
【Semiotics】面からも追っている私です。
カタカムナ文献(全80首の歌)の内容を追っていると
どうやら「現象界の成り立ちをミクロな目線で追っている」ってことはわかる。
はじまりが潜象界の根源の力で、それが現象化に向け
「ヒ・フ・ミ・ヨイ」と変還していくわけでしょ~
そこで私はカタカムナを「物質のはじまり」から探っていくことにした。
カタカムナが説く世界を理解したくとも
「私の知っている範囲で私の理解できる範囲」に限られてしまうので
できるだけ今の自分の知識を外側に持っていく方向で…
と、最近の私は「ゆっくり解説動画」でミクロの世界を学んでおります。
⇓
そこでまず、こちらを見ながら「はっ」としたわけです~
もう、このサムネだけで「カタカムナ文字」や~
「ヤタノカガミ」図や~ってなったわけです。
神聖幾何学だと「3」と「6」が基本となり
カタカムナ文字は十字と八方位が基準なので「謎」だったのです。
何からきてるのかな~って。
んで、カタカムナは生命体を構成する最小のマリを「イ」としてますよね。
「イカツ=電気粒子」なので、ボーアの原子モデルを見て「あ!」となった。
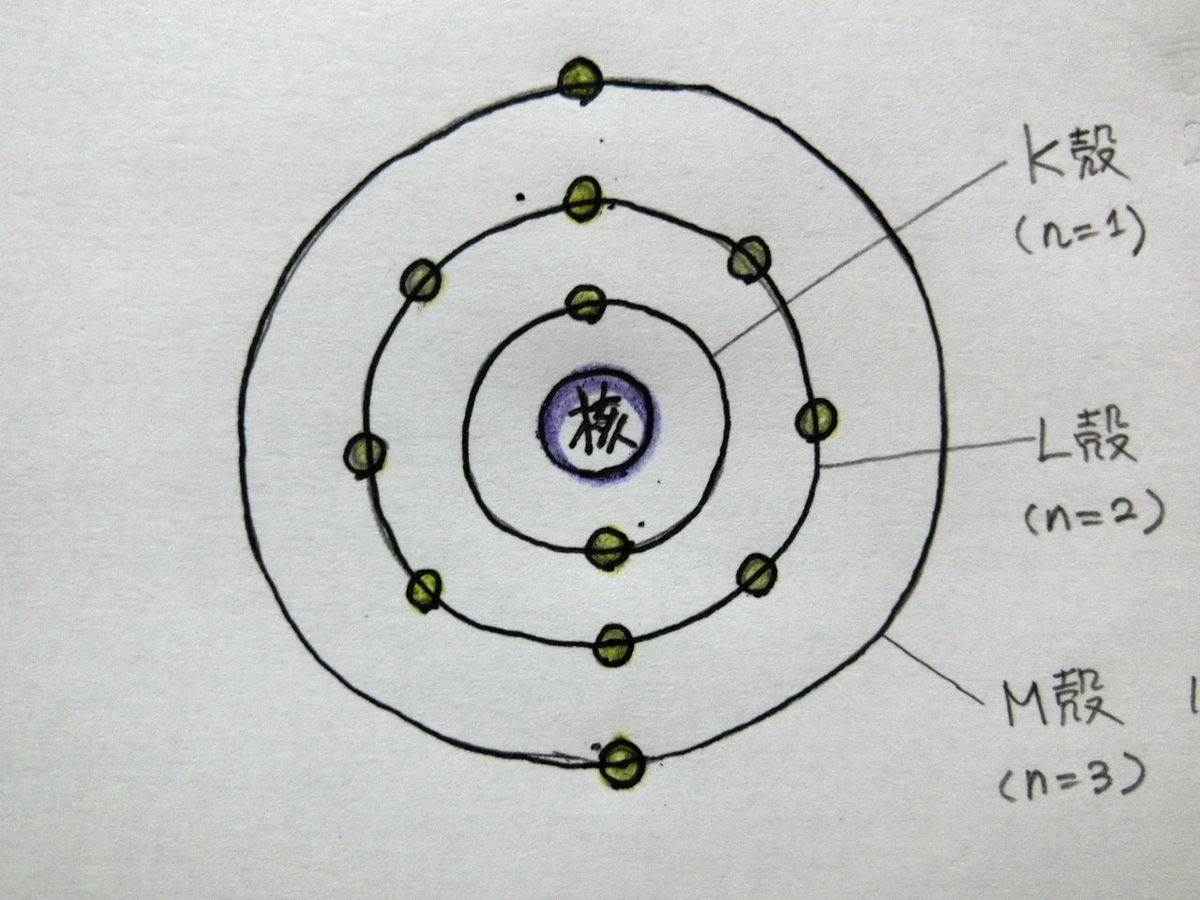
カタカムナ人は超古代時代にして既に
「ここまで見えていたのではないか?」と思えたのです。
原子に核(ミナカヌシ)があって
そこに「イ粒子」がどうやって纏まっているか?
L殻に注目してほしい⇒もうカタカムナのヤタノカガミ図や~
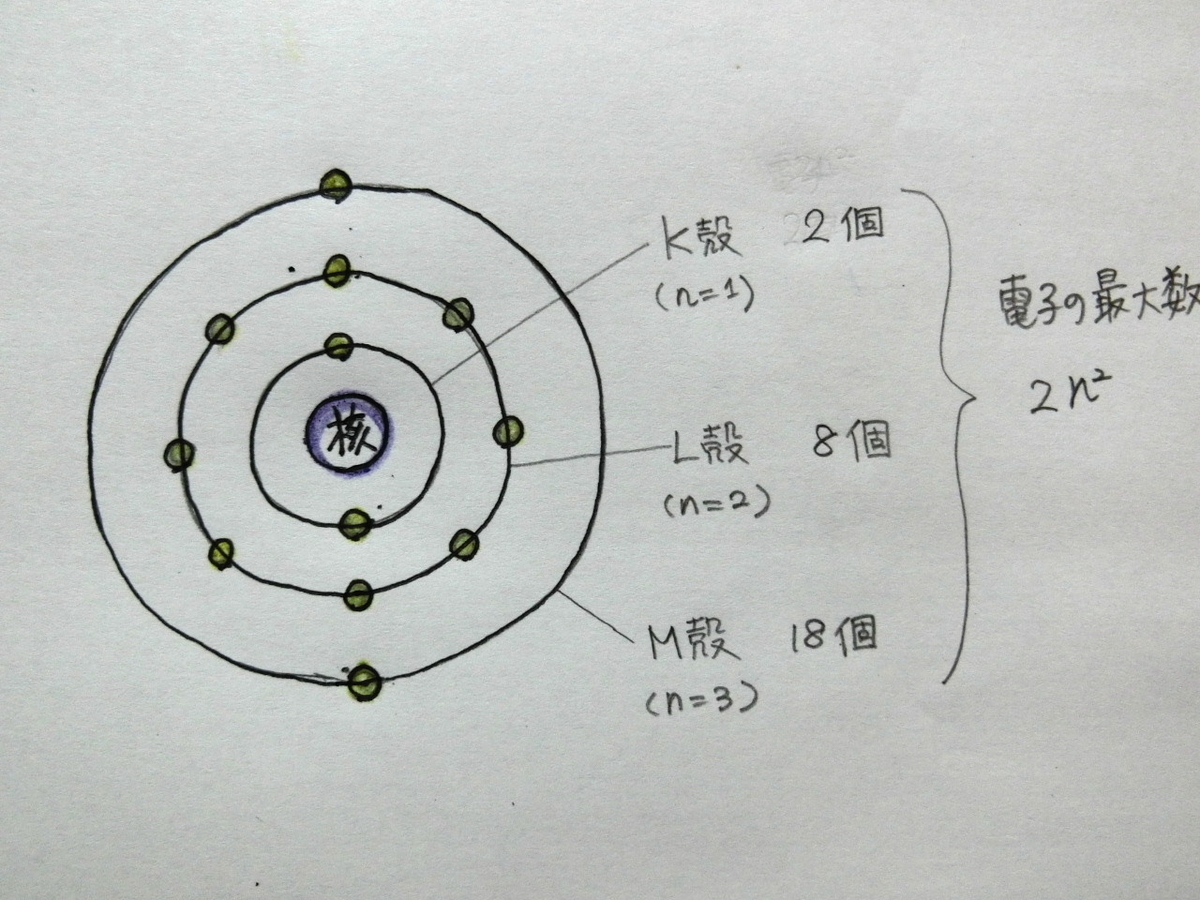
んでな、ボーア原子モデルから電子の位置を「電子軌道」=電子雲・確率雲で
見ていくと「イモ」って言葉の意味がよく分かってくるのだよ!!
だからカタカムナ人は「イが藻のように漂う粒子」だと知っていたんじゃないかと。
しかも原子核に対する「安定形状」まで知っていたんじゃなかろうかと。
それに、ここからはじまって
結構がっつりと繋がってくるのだよ~(若干怖いほど)
あと、ずっと詳しく言及するのはずっと先になるかもしれないが
カタカムナ文字が複数音を1文字で合わせ表記する時に
抱いていた疑問の「解」として
「カタカムナ人は3つ目の眼を持ち、
この世界を我々より高次元的に見ていたんじゃないか?」
と思えてきたのです。
イメージ的に「位相幾何学」の視点で見えていたのかな?と。
我々が3次元認識している空間は
- ソコ(膨張~アワ)
- ソギ(収縮~サヌキ)
- シマ(流線~ナミ)
- マリ(粒子~ナギ)
の性質と力の変還作用によって
粘土のように常に練り転がされ変形しているのかもしれません。
そんで出来るだけ「複雑な形」を目指しているのかもね。
つづく



