
第四の嶋は現・九州や~
こちらも非常に興味深い「姿・形」しております。
古代日本の叡智に触れる為、奔走中の私です。
古代日本語~日本語のヒビキの神秘構造に触れ、今やっと「古事記」の解読へ~
では、隠岐の三つ子嶋の次の嶋をみていくで~
⇓
次に筑紫嶋を生みたまふ。此の嶋も身一つにして面四つ有り。
(「古事記」より)
筑紫嶋(つくしのしま)も身一つにして面(おもて)が四つあるのです!
伊豫の二名嶋(現・四国)と似てますね。
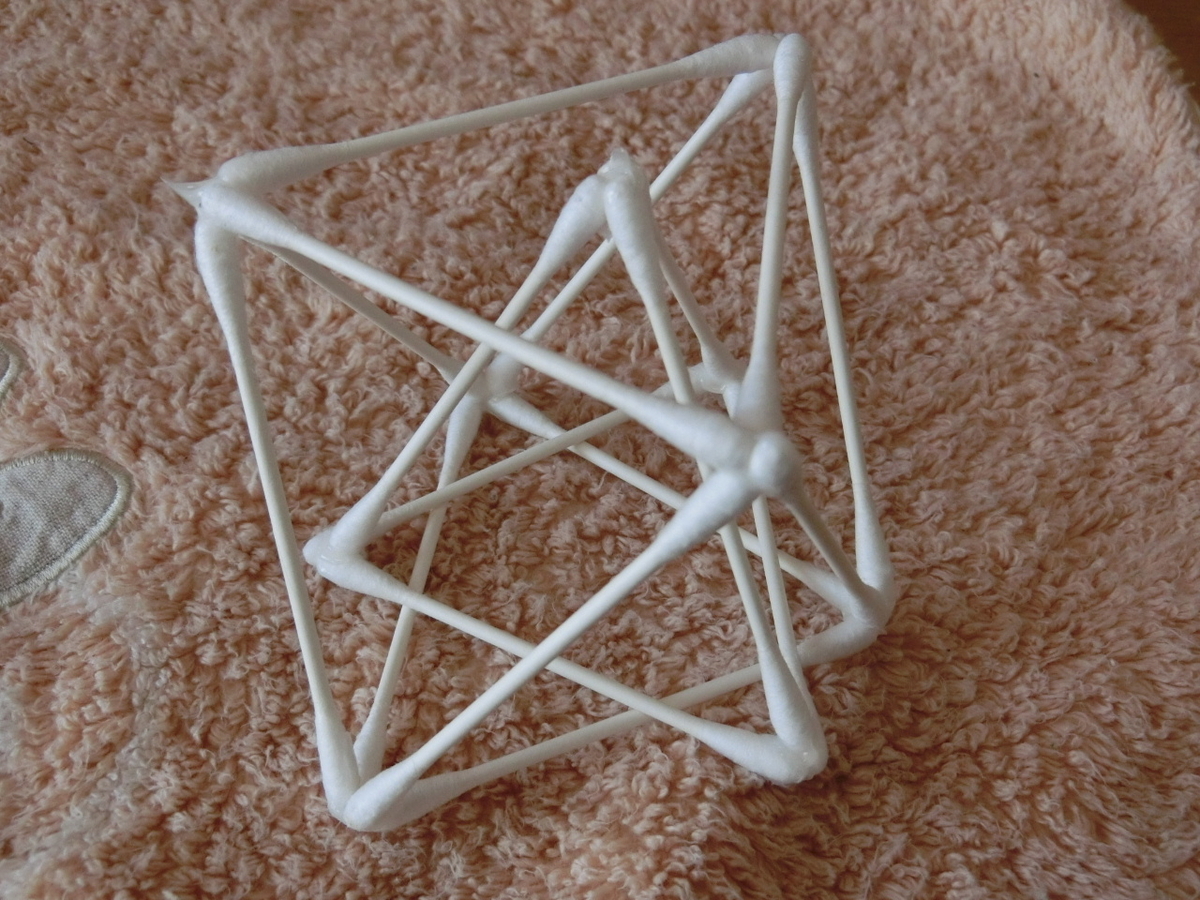
正四面体というよりは、私としては「嶋・国=物体・有形・生命体」というエネルギーがとても固く重く結合した塊というのは基本的に正八面体(構造)の上半分部分が現象として現れたものなのだと思うております。
では、まずは「筑紫(つくし)」という名・詞が示すものを読み解いてまいりましょう。
⇓
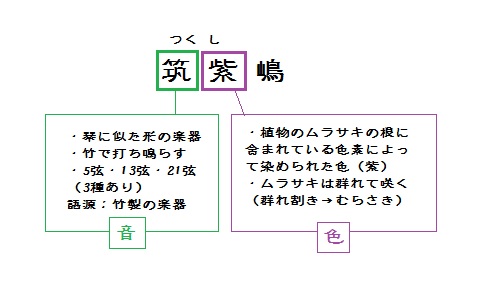
「筑紫」とは、
- 神聖な「音」
- 神聖な「色」
という「神聖なヒビキが音や色となって現象化する」ことの示しではないでしょうか。
注目すべきことは、アマ界(この現象界)を満たす神聖なヒビキ(振動・振動波)というのは「竹」や「ムラサキ」が示すように「植物(地の生成)」によりもたらされるということなのです。
なんとなく「植物文明界」に行った異世界体験談の信憑性増した気がする。
(つづく)


