
進み具合が「鈍足」ですが、カタカムナのウタの示しの解読にのめり込んでる私です。
第42首の内容に腰を抜かす”気づき”を得まして、
今まで以上に興味・関心をそそられております。
◆カタカムナ第36首を詠む
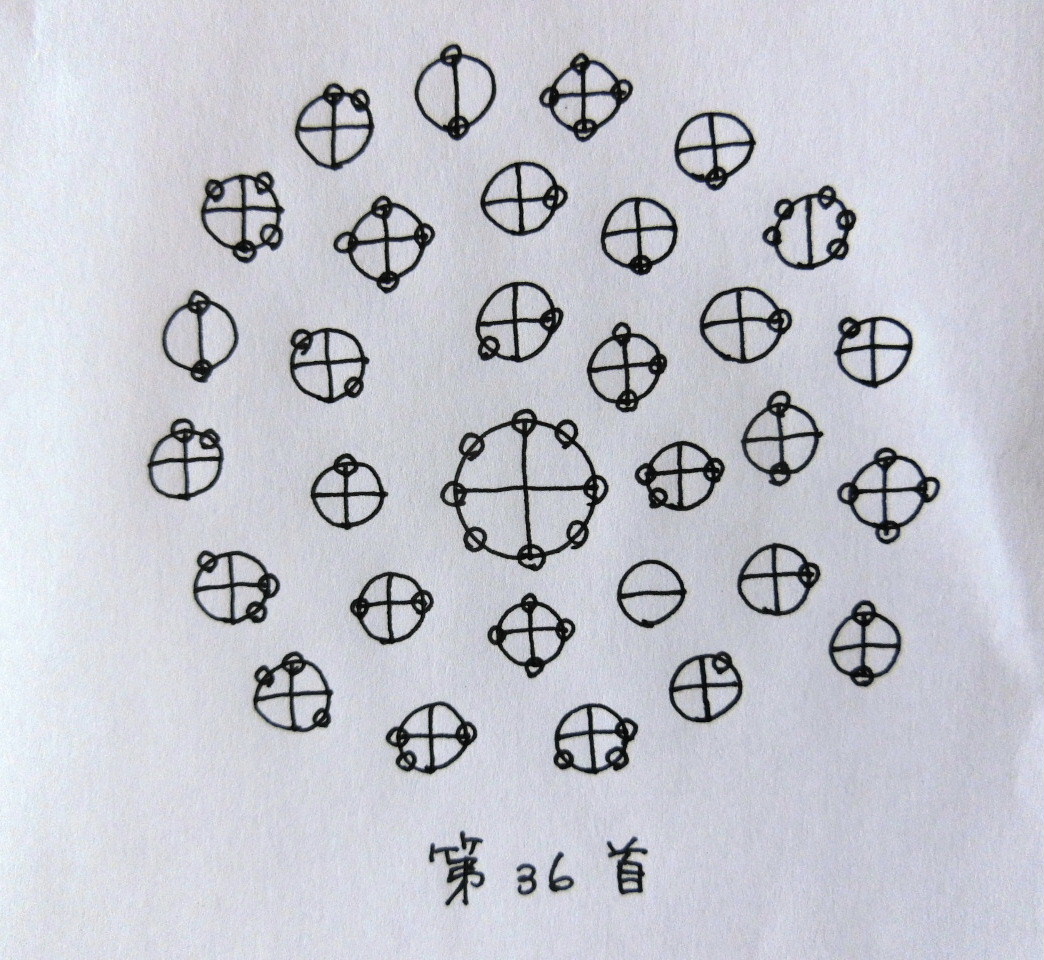
声に出して音を響かせイメージしましょう☆
【カタカムナ第36首】
オホトノヂ アメノミクマリ クニノミクマリ
ツラナギメグル トヨツラナミ
「カタフトムスヒ~クニノミクマリ」まで一気に行きたいところですが
ちょっと長いし「カタフトムスヒ」大事なんで前半・後半に分けました。
◆一音一音の示し
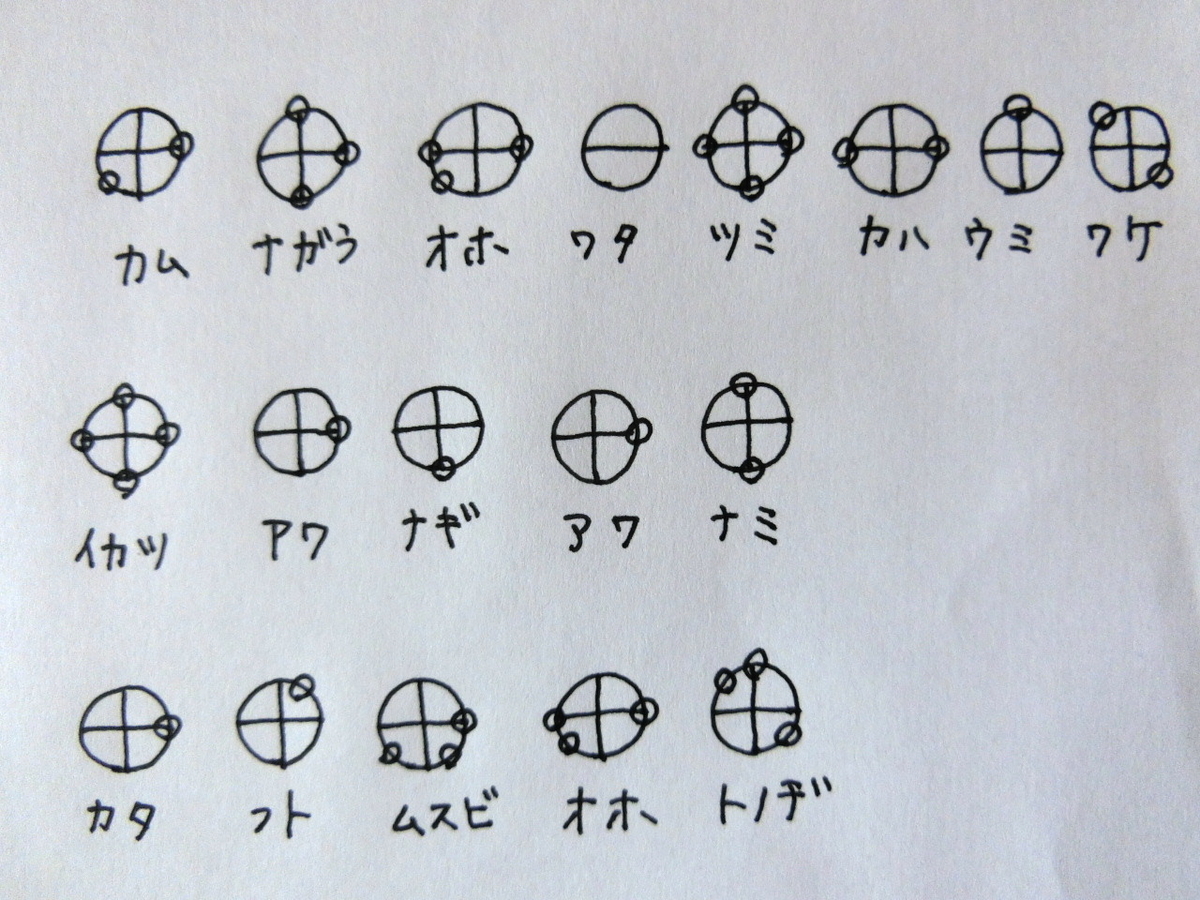
「カタフトムスヒ」
- カ(根源の力、ちから)
- タ(分かれ出る、独立発生)
- フ(増える、2つ、負)
- ト(重合、統合)
- ム(無、無限の、広がり、六方環境から)
- ス(進む、一方へ進む=方向性を以って進む、透けた)
- ヒ(根源から出入、最初のフトマリ、ひとつの)
「オホトノヂ」
- オ(奥深く、広がる、環境、六方環境)
- ホ(ほぐす、正反発生+正反親和)
- ト(重合、統合)
- ノ(時間をかける、変還する)
- ヂ(凝縮、持続的に)
では、ここから音を纏めて「ことば」にして解読を
◆カタフトムスヒ とは
カタカムナ文字の表記を見ると
「カタ」「フト」「ムスヒ」で音がまとめられております。
- 「カタ」=根源の力が(サヌキ・アワの力として)分かれでて
- 「フト」=2つが重統合され
- 「ムスヒ」=「ヒ(粒子)」を発生させる
⇓
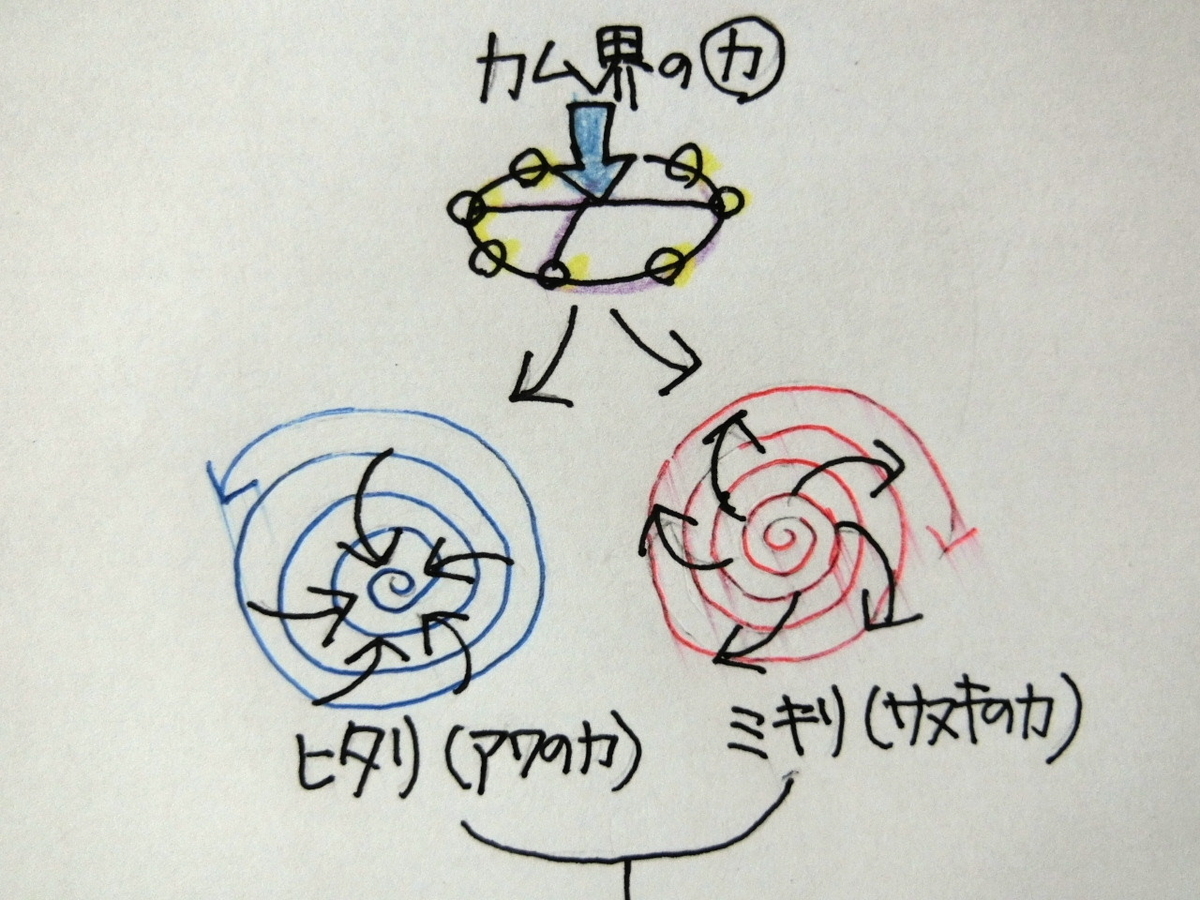
⇓
2つに分かれ出た力が、引き合い1つの纏まりになったのが
アマ現象界に生成力として発生した根源の力の変還「ヒ」粒子
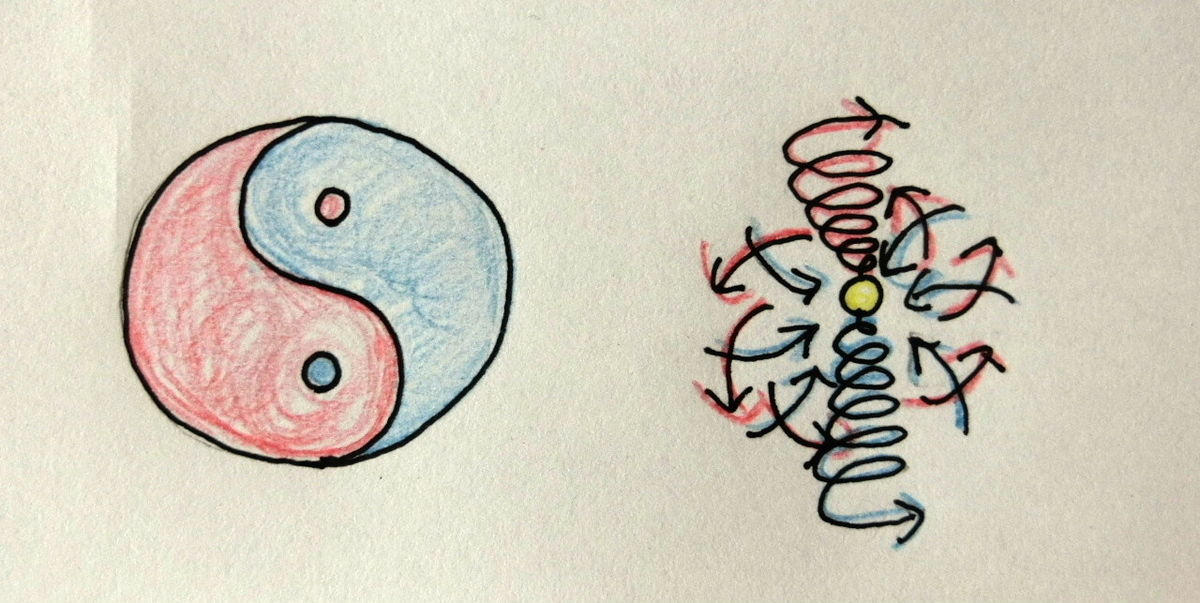
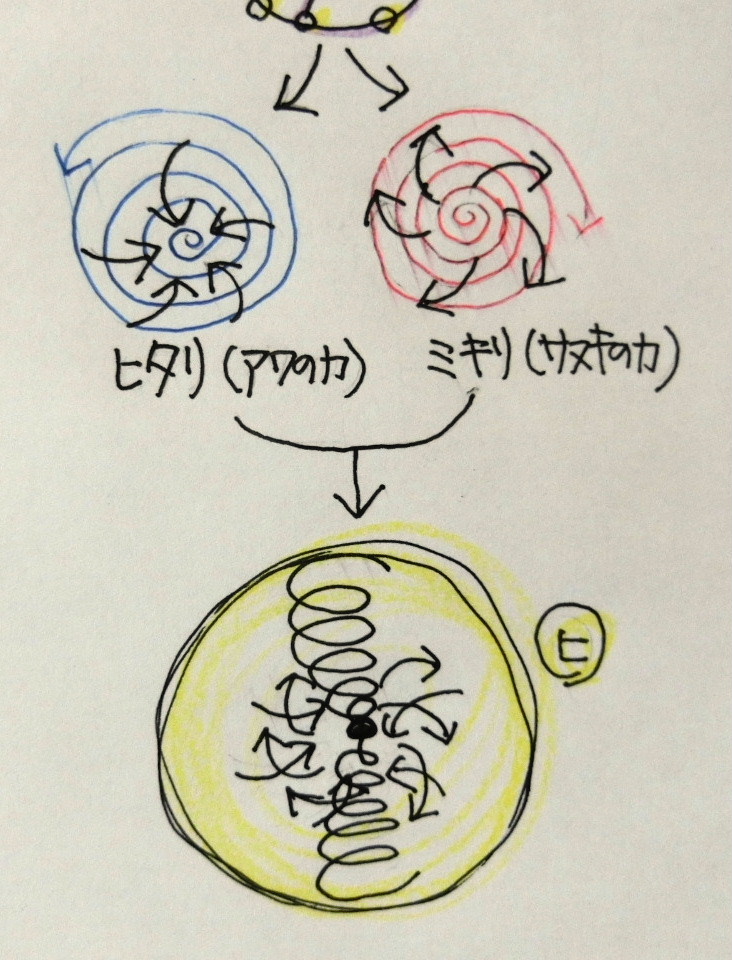
※今のところの私の理解と映像イメージ
◆「それ」がオホトノヂされ
「カタフトムスヒ」によって発生した
「アマ界に発生した根源力・ヒ粒子」が
オホトノヂされ
⇓

アマ界の現象化の環境(場)に親和重合をくり返し(持続)して「練り込まれ」
⇓
んで、ここが前の部分とどうつながっているかというと
”「カ」から「タ」した「フト」によって
という意味になっているらしいっす(まだ私は漠然とした理解どまり)
※オホトヒワケでそうなるのかな?と今は理解中
そんで、更に次に続く「アメノミクマリ~クニノミクマリ」に成っていくわけです~
(つづく)


