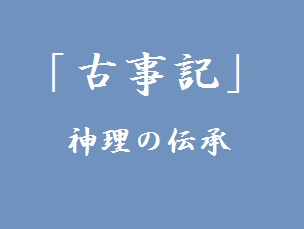
もしかして、我々の世界の前時代(前に在った世界)って…
マジで「火の鳥」みたいな展開になってきたのか??
やはり日本語は難しい…古代の智恵が詰まった「日本語のヒビキ、音の構造」を100%理解して使いこなしたいのに、まだまだわからぬ部分もたくさんでてくるよ~
日本人として、古代日本人がせっかく智恵を積めこんだ「日本語」を伝授してくださったのに、理解不十分で使いこなせない私の不甲斐なさを痛感しております。
ぼやいてても、嘆いていても進歩は無いので先に進んでいこう!
⇓
では、美斗能麻具合の神髄「言葉の唱和」の部分の後半の解読へ
⇓
約り竟へて廻る時に 伊耶那美命まづ「あなにやし、えをとこを」と言ひ、後に伊耶那岐命「あなにやし、えをとめを」と言りたまふ。
(「古事記」より)
「あなにやし、えをとこを(ああ、愛すべき若君よ)」×「あなにやし、えをとめを(ああ、愛しい乙女よ)」
ここで「男=をとこ」「乙女=をとめ」であることに注目!
我々が認識する「男性・女性」という意味以上のなにか意図が込められている気がするのです。
ちなみに「を」の音に当てられていた漢字の意を調べようとしたんですが…でてきませんでした。「袁(両手に服をもってきている様)」この字に近いけど…
- をとこ(男)=を登古
- をとめ(乙女)=を登賣(売)
ここで私なりに「をとこ」「をとめ」の音に当てられた漢字から そこにある意図を探ってみた。
⇓
「を」は「お」に行く前の「現象(現象化)の立ち上がり」を示していると思われます。カタカムナで「ヲ=~を以って、奥に出現する」ということは「えをとこ・えをとめ」で一塊の言葉なのか?
「登」「古」「賣(売)」の示す意味や成り立ちを調べてみると、
- 「登」=”器に盛った食べ物を捧げ上方向に昇っていく足”を示す字
- 「古」=遠い過去の、遠い前の時代の
- 「賣(売)」=財・利益を求め物を出して金を得ること(物⇔金)
なんとなくですが
が示されているような気がしております。
更に現代の漢字では見当たらなかった「を」に当てられていた字が「袁」に極近い意味をもっていると考えた場合、「人間の男性と女性」というのは…そういった上昇力やエネリギーの変遷・循環が衣を纏ったもの(のウツシ)だということではないでしょうか。
んで、私の勝手な解読をそのままここに書き散らしておきますと
「古」が指し示す「人間の世が創造される前時代」遠い遠い過去・前時代って…「草文明の時代(自由に動き・様々な能力をもった植物たちが大地の主だった時代)」ではないかと思えるのです。
時折、この世界に迷い込んで戻ってきた方々が「植物世界」の体験を語ってくれている。
⇓
こっちの動画は、後半にある「掲示板に現れた読める人」の解読に注目っす。
神(根源)の意図によって「植物⇒人間」が創造されていく様子を古事記も描いているのではないだろうか。
「葦・青草」が人間を示すというのも「葦・青草」が人間の「もと」だからと思うと納得できる。
神世七代から「人間世界の創造」が始まっているのかもしれない。
ただ、人間世界というのはそもそも「神人を創造する世界」が目的であったように思う。それがどんどん「神人の中で神霊力が小さくなっていき、人の業(エゴ)が強くなって人間」になっていってしまったのかも。だから「えをとこ・えをとめ」の「え(愛)」がとれちゃったのかもね、人間の男女から。
(つづく)



